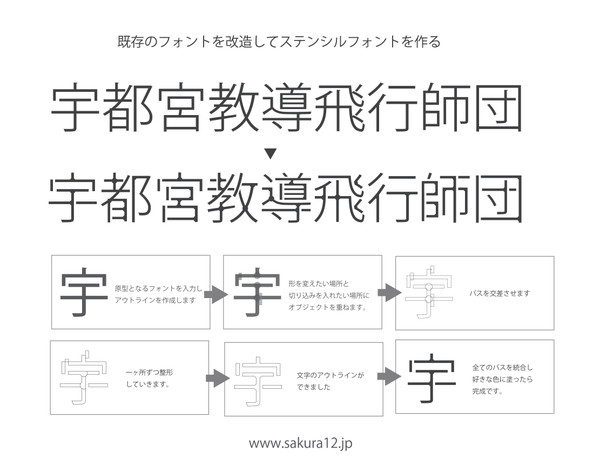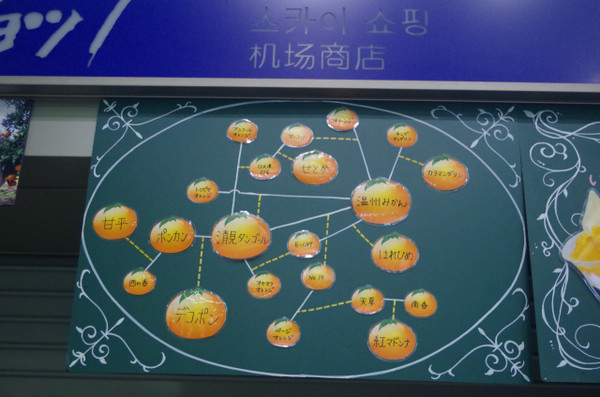一式陸攻の搭乗員だった
天野環さん(93歳)にお話を伺いました。
天野さんは三沢海軍航空隊、のちの
第705海軍航空隊で一式陸攻に
搭乗し、東京初空襲呼応、ミッドウェイ
海戦、ソロモン海戦に参加した方です。
インタビューに
快く応じてくださり、本当に感謝です。
一式陸攻で戦ったお話を、少しずつ
書かせて頂きます。以下、天野さんの
お話です。

◆一式陸攻に乗るまで
私は最初は呉海軍工廠に努めよったよ。そこで戦艦大和の一部を造っとった。
呉は日曜や祭日になると駆逐艦や巡洋艦から上陸した水兵が歩きよる。
それ見て「ああいう風な海軍の兵隊になりたいな」思うてな。
それでいずれ志願するんやったら飛行科がいい。
「飛行機に乗ったる!」と思うてな、呉で志願して呉の海兵団に入団したんじゃ。
海兵団入って、丙種予科練に合格たんじゃ。丙種予科練、丙飛と言うが、
予科練には甲飛、乙飛、丙飛と三種類あるんじゃ。その中でも丙飛が
一番戦死率が高い。甲飛は当時の中学、今の高校じゃ。これを卒業した者が
志願して入ったのが甲飛。乙飛は小学校卒業してから入る、いわゆる
少年航空兵じゃ。
そして丙飛。この丙飛と言うのが一番使い道がええんじゃ。
何故か言うたら、まずはそれぞれ所属の海兵団に入って
一般の兵隊、それぞれ専属の兵科を半年くらい経験してから
飛行科を志願したのが丙飛なんじゃ。せやから、本当は丙飛が
一番優秀なんじゃ。
これは名前の付け方が悪いよ。何も知らん者は、甲乙丙言うたら
一番丙が悪い、ボロじゃと思うもんね(笑)わしはその丙飛じゃった。
自分の名前よりは兵籍番號。今でも覚えとるよ。〇〇〇〇じゃ。
呉海兵団へ入団したのが大凡3900人。そこから予科練行って
霞ヶ浦で練習生になったんよ。
霞ヶ浦でエンジンの分解組立や、基礎的な事を習って、今度は実際に
飛行機に乗るようになるんじゃが、これは岩国の航空隊じゃった。
あそこで初めて赤とんぼ乗り出したんよ。その頃に大東亜戦争が
始まったんよ。
敵の潜水艦が瀬戸内海に入りよった言うから、私らは赤とんぼに爆弾抱いて
飛びよった。一番初めは九七練習機言うのが、あれ九〇やったか、
練習生が五人くらい乗れる練習機があって、それで瀬戸内海の上空
飛びながら射撃の訓練やら、偵察の訓練やら、色々やっていくんじゃけどね。
飛行科はね危険加俸と言うのが付くんじゃな。今でも飛行機乗るには
住所名前書かにゃならん。いつ墜落するかわからんから。汽車は無いでしょ。
飛べんかったらポトンと落ちよるんよ。だから危険加俸が付く。
その他には、朝方と、晩方の飛行。これにも付く。
朝は黎明(れいめい)飛行。晩が薄暮(はくぼ)飛行。
ちょうど日の暮れ方、明け方が危ないんじゃ。特に離着陸は。
だからこれも危険加俸が付く。
ただ飛行機に乗るだけではいかんのよ。上空で機上作業せにゃいけんのよ。
電信やったり、機銃をドンドンドンドン撃ったり、この撃つのがまた難しいんでな。
吹き流しを50メーター離れたとこから、撃ち込まなきゃならん。
あんまり前だと曳的機撃ってしまう。といって、後ろへやると弾が流れて
しまって当たらん。ほいで4、5人が乗っていっぺんに打ち込むんよ。
弾の先に色付けて赤じゃ紫じゃ無色じゃ言うて。誰が赤じゃ、紫じゃった
言うのは解っとるから、吹き流し落として、赤がなんぼ、紫がなんぼ言うて
ヘタクソは何回でもやらされる。
それぐらいじゃ済まんよ。何も悪いことせんでもビンタくらいは軽い事。
バッターいうて最低10回。多い時は30回くらい。それでフラフラして倒れると
「貴様これくらいで」とひっぱっていって、またバーンと徹底的に気合
入れられるよ。今の若い者じゃ、とてもじゃないが無理じゃ。
「逃げたい奴は逃げ!死にたい奴は死ね!」
言うて、逃げて帰る訳にはいかん。万歳万歳で送り出されとるんけん。
今ならええよ。上官が酷か言うて帰ったら、上官のほうがやられるかもしれん。
昔はそんなもんじゃない。
しかも軍隊では一階級違っただけ天地の差があるんよ。
私はサイパンにおったときに非戦闘員に殴られたよ。
非戦闘員言うのは医官と、飯炊き。戦争しやせん。
それに私は殴られてな。それでも一階級上だからしょうがないのよ。
あそこでは私が一番若い兵隊じゃったから。食事当番じゃ。
一機ずつ索敵に出るんじゃから、敵の機動部隊見つけたら原隊に報告して
爆撃なり雷撃なり行かにゃならん。大型機じゃけん、私のペアが7人居る。
(海軍では同じ機体のクルーを三人以上でもペアと呼称した)
飛行から帰って、食事を取りに行った。そしたら食卓の兵隊が一等兵。
私は二等兵じゃ。「貴様、取りに来るのが遅いじゃないか」と言って
ボンボンボンボン殴られて。ほいやけど自分らのペアが待っちょるけん、
泣きながらでもご飯持って行って。わしは悔しかったよ。ほんまに。
操縦だった坂井兵曹が・・・ああ、坂井兵曹も後に死んだよ。
死ぬとこ見たよわしゃ。・・・その坂井兵曹がわしを見て
「天野、どうしたんだ、なんで泣いてるんだ」と聞く。
「こういう訳です」なんて言うたら次に行ったらまたやられるけんな、
わしゃ黙っとったよ。自分に言い聞かせたよ。
飯炊きに叩かれてどうすんじゃ!あんなもん非戦闘員じゃが!
戦をするのは我々ぞ!叩かれたくらいでどうすんのじゃ!そう思うてな。
Q、篠原
ずっと同じペアだったのですか?
A、天野氏
ええ、一式陸攻乗ってからずっと同じ。
東京初空襲、ミッドウェイ、ソロモン海戦で皆戦死するまでずっと一緒。
一式陸攻の321号機じゃった。三沢海軍航空隊。
のちの第705海軍航空隊。300番台が攻撃機じゃったんよ。
一式の尾翼に番号が書いてあって上に白い直線が一分隊。
私は二分隊じゃけん真ん中の線じゃった。三分隊が線が縦になっとん。
私は321号じゃった。私は一小隊の二番機じゃったんよ。
◆一式陸攻のクルーとそれぞれの役割
Q、篠原
一式陸攻の搭乗員について教えてください。
A、天野氏
一式陸攻は7人乗る。操縦員がメインとサブで2人。
右の席がメインで左がサブ。偵察員もメインとサブで2人。
飛行機にもよるが私のとこは機長がメインの偵察員で
私がサブの偵察員で一番前の席におったけん
それと、電信員、搭発員(搭乗整備員)、射爆員、それで全員じゃな。
木更津辺りで訓練する時は、一式陸攻は一機ずつの着陸じゃったけど
零戦は小さい飛行機じゃから三機編隊で離着陸しよったで。
Q、篠原
操縦もされたのですか。
A、天野氏
操縦員が撃たれて死んだら、どうするんじゃ。
操縦も知っておかにゃ。一式乗りは何でもやる。
通信もですよ。専門の電信員はモールス信号を最低でも120以上。
それ以外の搭乗員でも100は打ったり受けたりせにゃならん。
トンツートンツートントン。それも知らんじゃったら飛行機乗れんよ。
電信員が死んだら自分がせにゃいかん。一式陸攻乗ったら、何でも
出来なきゃならんのよ。操縦が出来ません、電信が出来ませんじゃあ
通用せんのよ。戦地へ行かせてくれん。出来るまで内地で一生懸命練習じゃ。
射撃もせにゃいかんよ。機銃ドッドッドッドッ撃つ。
Q、篠原
一式陸攻の操縦はどうのように行うのですか
A、天野氏
まず、計器はみんな英語になっとんじゃけんな。
パイロットも偵察員も皆、英語を習わされる。その計器を見ながら、
ボボボボ吹かしていったり、飛ばしていったりする訳や。
ハンドルはもう、これ(持ってるだけ)着陸のときだけちょっと難しい。
離陸したら自動操縦装置に切り替えて、例えばサイパンならサイパン、
〇〇度、〇〇マイルと、地図で見て南方へ行くんじゃったら
180度じゃろ。それ考えてな。高度三千なら三千に決めて、
それに合わせたらあとは自動操縦装置でも構わん。
操縦員は操縦専門以外に偵察を習っとかなきゃならんが
偵察員も操縦くらいやらなんだらいかん。
Q、篠原
兵器の扱いについて教えてください。
一式陸攻は30キロ爆弾じゃと12発。500キロで2発。
魚雷は800キロやから一本しか持てん。最大で1トン、プラス
200か300キロなら積んだ。30キロ爆弾を12、3発積んで
それを同時投下、あるいはタンタンタンと一個ずつ落とす。
艦船の場合は同時投下やな。照準器を見て
「爆撃用意(ばくげきよーーーい)」
「チョイ左、チョイ右」
言うて標的がレンズの十文字に重なってくる。
「投下用意(とうかヨーーーーイ)
言うてレバーを下げたら、レンズの都合で標的がいっぺんにサーっと
逃げるんじゃ。実物が逃げるんじゃなくて(機体の速度に対して地上の
目標が静止しているため)それで十文字の真ん中に丁度来るように操縦を。
うまいことうまいこと「チョイ右」「チョイ左」で合わせて
「ヨーソロー」「投下ヨーーーイ」「投下ーーー」
言うて落とすんじゃけどね
その訓練をサイパン島でやったよ。高度8000で。訓練で使うのは
煙硝爆弾。煙硝爆弾はガラスになっちょるから落ちたら割れて
煙幕がモクモクモクモク上がって、高度8000から見ても分かった。
今度、雷撃はね、大分の航空隊におった頃から、別府湾の沖でやりよったよ。
昼挟んで午前と午後とで交代して訓練やったよ。魚雷は一度放ったら
終わりやで、それで擬雷ゆうの使って。ヒレが無いといけんのじゃ。
あれは強板言うてな、ベニア板。強板があるから爆弾みたいに
そーっと落ちるんやがな。そうやって色々やったよ。
一式陸攻で土佐沖の艦隊訓練にも参加しとる。木更津から土佐沖まで
飛んで行って、上空から陸奥、長門が取り巻いて、その中でも
一番大きなのが大和じゃった。空から見たよ。
「おお、あれが大和じゃ」言うて。それでずーっと低空で飛んで、
雷撃訓練やったよ。
雷撃は実戦では三回行ったよ。東京初空襲の時(ドゥーリットル空襲)と
ミッドウェイ海戦と、ソロモン海戦。爆撃より雷撃のほう絶対、命中率が
高いけんな。魚雷抱いて敵の艦船のマストスレスレの高さで飛んで
だいたい1キロくらい手前で魚雷落とすんじゃけんな、ほいじゃが
飛行機のほうが魚雷よりちょっと速い。後を見よったら命中したの
すぐにわかるけんな。
一式陸攻搭乗員天野さんのお話(2)
東京初空襲