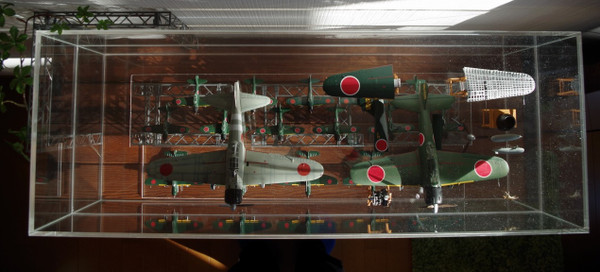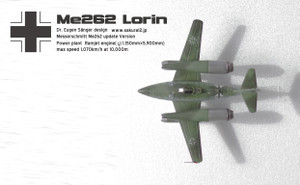捨てられなかった札束 濁流にのまれた慰安婦

戦友会でも慰安婦の話題になったことがあります。
もっと確信に迫る話しがあるのですが、今回は証言の一端を紹介します。
K曹長の話
「濁流を渡河する徹底路において、日本兵と一緒に逃げる女性(慰安婦)を見ました。
よく見れば頭の上に大きな荷物を乗せているんです。少しでもバランスを崩せば
濁流に飲み込まれて一貫の終わりですよ。それでも両手で必死に頭の荷物を
押さえているので、縄につかまることさえ出来ません。その荷物、
捨てろ!捨てろ!と叫んだんですが、女性は捨てませんで、今にも濁流に
流されそうでした。その頭に抱えている荷物、良く見れば、大量の
お金、札束(軍票の束)なんです。慰安所で稼いだものだと思いますが、
死んでしまってはおしまいですから何度も捨てろと言い聞かせました。
それでも聞かず、最後は濁流に呑みこまれていきました」
Y上等兵の話
「当時、私の月の給料は戦時加算がついて24円50銭でした。
ところが、その慰安婦と呼ばれる女性たちは1万円も2万円も
持っていたことに驚きました。
いわゆる慰安婦はもとは貧困で身を売ることしかできなかった
家の娘がやむなく行っていた。このエピソードはとても悲しいものだが
稼いだお金を命がけで故郷へ持ち帰ろうとしていたものなのかも、しれない。
慰安婦についての証言はまだまだあります。
続きます。